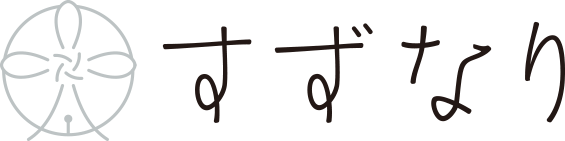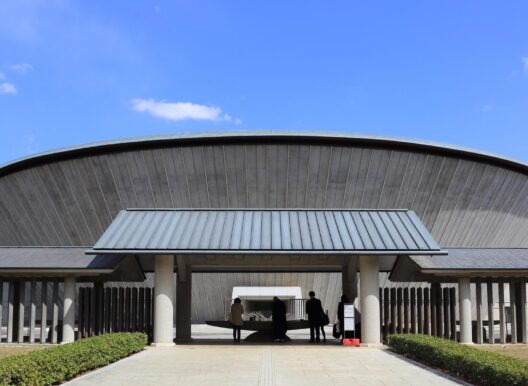近年では、少子高齢化や核家族化が進む影響で後継不足などの影響でお墓の管理に悩まれる方が増えているようです。
そのために、墓じまいを選択するケースもあるようですが、実際に墓じまいをした後に遺骨をどのように供養したら良いのか分かりにくいでしょう。
ここでは、墓じまい後の遺骨の供養方法、そして遺骨を取り出す際の注意点についてなど解説します。
Contents
墓じまいとは何?
墓じまいとは、所有している墓石を撤去・解体して土地を元の更地の状態にして管理者に使用権を返還することを指します。
お墓に納められている遺骨を、ご自身で勝手に取り出して持ち帰ったり別の場所に納骨したり、廃棄したりすることなどは法律で禁止されています。
遺骨の移動は、必ず事前に行政での手続きを行った上で実施することが必要となります。
墓じまい後の遺骨の供養方法

親族の中で様々な話し合いの結果、墓じまいを選択することになりますが、墓じまいをした後もどのように故人を供養するのか事前に決めておく必要があります。
墓じまい後の供養方法は以下のような種類があります。
永代供養
永代供養とは、期限を設けることなく弔いをするという意味で、遺族や子孫、親族などに代わって霊園や寺院などの管理団体がお墓の維持管理と供養をすることを指します。
子供に墓守の苦労をかけたくない場合や、後継者がいない場合、お墓に関連する費用を工面できない方など様々な方の事情により選ばれる方法です。
手元供養
手元供養とは、故人の遺骨の全部または一部を自宅等の身近な場所に保管する供養方法のことを指します。
手元供養の方法としては様々な方法がありますが、遺骨を専用の容器やペンダントなどに入れて持ち歩く供養を「手元供養」、遺骨全数または一部を自宅で保管する供養を「自宅供養」と呼ばれることがあります。
遺骨を身につけたり、日々共に暮らしながら故人を供養したい方などに選ばれます。
散骨
散骨とは、火葬した後の遺骨を粉末状に砕いて、遺骨の粉を海・山・空などに撒いて自然に返す供養方法を指します。
国内では、近年知名度を上げている供養方法になりますが、古くは平安時代より行われている葬送方法のひとつとなります。
生前に故人が散骨をしてもらいたい場所などを、自由に選択することができます。
改葬
改葬とは、墓じまいを行った後に遺骨を取り出して、別のお墓に移動させることを指します。
簡単に説明すると、お墓の引っ越しになります。
お墓が遠方にあり管理できない場合や、利便性のよい場所への移動、夫婦両家のお墓をひとつにまとめる際などに選択されます。
墓じまいで手元に遺骨を残さない選択肢もある

先祖の遺骨を処分することは、従来のような考え方であればバチが当たるような印象がありますが、現在では生活の多様性や様々な宗教観の違いなどにより、手元に遺骨を残さない選択肢も多くなりました。
前述の散骨も、墓じまい後に遺骨を残さない代表的な供養方法ですが、その他にも遺骨を残さない方法があります。
どのような場合に手元に遺骨を残さなくするの?
墓じまいを行った際に取り出した遺骨には、遠い先祖の遺骨もあれば比較的近くで思い出深い両親や配偶者の遺骨などもあると思います。
先祖代々受け継ぐ遺骨全てを安置して、後世まで供養したい気持ちはありますが柱数が多いと管理が大変で経済的な負担も大きくなります。
そのために、墓じまいなどのタイミングで先祖の遺骨を合祀する形で処分するケースが多くあります。
遺骨を手元に残さない供養方法としては次のようなものがあります。
散骨
散骨は、前述のように火葬後に遺骨を粉末にして海、山、空に撒く供養方法のことを指します。
生前に個人が他界した後には自然に還りたいなど遺言を残していた場合や、家族の意向により選択されることがあります。
遺骨を自然に還すことから「自然葬」などとも呼ばれます。
遺骨はどのような場所にも勝手に散骨することはできないので、ご自身で散骨場所を選定できない場合には専門の業者に依頼を行います。
散骨にもタイプ別に次のような種類があります。
海洋散骨
海洋散骨は、生前釣りや海が好きだった方が選択することが多い散骨方法です。
あらかじめ専門の業者などでチャーターした船舶に乗り、散骨が可能な海洋地域まで移動して散骨を行います。
条例により禁止されている地域もあり、事前に確認して散布する必要があります。
また、禁止区域ではなくても海水浴場や漁場近くで散布するとモラル的に良くないので、一般的には沖に離れた場所で供養を行います。
一般的に観光地とされている場所や、沿岸部、川や湖などは散骨することができないので注意する必要があります。
山林散骨
山林散骨は、生前登山や山に関するお仕事をされた方など、山に思い入れがある方が選択する散骨方法です。
山林で散骨する際には、どこにでも散布しても良いのではなく、土地の所有者に許可を取る必要があります。
また、水源近くへの散骨は禁止されているのとともに、土の中に埋める行為も墓地埋葬法に違反するので注意が必要です。
空中散骨
空中散骨は、セスナやヘリコプターなどで海洋沖に出向き空から散骨する方法です。
飛行禁止エリアなどもあるので、事前に決められた場所で散骨を行います。
故人の故郷が近隣にある場合には、ご自宅や職場、思い出の場所を上空で旋回してお別れすることも可能な場合もあります。
空中散骨の中には、バルーン葬と言われる散骨方法もあります。
これは直径2m~2.5mの大きな風船を空に飛ばして、成層圏まで辿り着かせた後に空中で破裂させて遺灰を空に散布する方法です。
合祀墓
合祀墓と永代供養を同じような意味と間違うことがありますが、異なる意味をなします。
合祀は、複数の遺骨を同じ場所で一緒に埋葬して管理を行うことで、永代供養は前述のように頻繁にお参りができない遺族に代わって寺院や霊園が永代に故人の供養や管理をすることを指します。
合祀墓の埋葬タイプ
合祀墓の埋葬タイプには次のような種類があります。
慰霊碑型合祀墓
慰霊碑型合祀墓とは、遺骨を納骨するスペースの上に目印として大きな石碑や仏像、お釈迦様などのモニュメントなどが建てられているタイプの合祀墓のことを指します。
合祀墓の中では、最も一般的なお墓になります。
一般的なお墓と同じようにお参りすることが可能で、線香を焚いてお花のお供えもできるケースがほとんどです。
納骨堂型合祀墓
納骨堂型合祀墓とは、納骨堂に合祀用のスペースが設けられている屋内形の合祀墓のことを指します。
一般的に納骨堂は、契約した期間を満了するまでの間は個別の骨壷に入れて埋葬され、その後に最終的に合祀されます。
一方で、納骨堂型合祀墓のほとんどの場合は、納骨時から合祀されます。
個別で供養されている納骨堂と同様にお墓参りを行うことができます。
立体型合祀墓
立体型合祀墓は、地上と地下の二段構造になっている合祀墓のことを指します。
立体合祀墓への納骨は、一定期間地上にて安置された後に、地下の合祀専用スペースに移されます。
限られたスペースを有効的に利用するタイプのお墓となります。
樹木葬
樹木葬とは、「墓地、埋葬等に関する法律」により許可を得た霊園や墓地に遺骨を埋葬し、墓石の代わりに樹木を墓標として故人を供養することを指します。
樹木葬は、基本的にお墓の後継を必要としていない永代供養に分類されるので、個人や夫婦で利用されるケースがほとんどです。
山林散骨を同様の供養方法と考えられる方もいますが、大きな違いとして山林散骨はお参りするお墓のようなものがなく、樹木葬は樹木が墓石の変わりをなします。
前述の合祀墓の種類の中のひとつとなります。
樹木葬の埋葬タイプ
樹木葬の埋葬タイプには、次のような種類があります。
合祀タイプ
骨壺から遺骨を取り出し、合祀墓のように他の遺骨と一緒にまとめて埋葬する方法です。
個別埋葬タイプ
他の方の遺骨と一緒にならないように遺骨を骨壺や骨袋に入れて、個々別々の区画に埋葬する方法です。
共同埋葬タイプ
遺骨を骨壷や骨袋に入れた後に、ひとつの大きなスペースに埋葬します。
合祀タイプと異なり、他の方の遺骨と一緒に保管はせずに個別管理して埋葬します。
墓じまいの際の遺骨の取り出し方

墓じまいの際には、全て保管されている遺骨をお墓から取り出す必要があります。
個人でもカロートの蓋を開けて取り出すことは可能ですが、墓石は非常に重たいので作業には危険を伴い注意する必要があります。
一般的には、専門の石材店に依頼を行います。
カロートにより取り出し方が異なる
九州・沖縄・関東・北海道地方に関しては、遺骨をできるだけ沢山集めて骨壷に入れます。
そのために、骨壷は直径21センチ程度になります。
一方で関西の場合は、喉仏を中心として一部分のみ遺骨を集めるので骨壷は9cm〜15cm程度の小型になります。
前述のように骨壷に大きな違いがあるので、カロートの大きさにも違いがでます。
九州・沖縄・関東・北海道地方のカロートは、大型で人が入りこみ遺骨を取り出します。
関西のカロートは、逆に狭い作りになっていると共に、骨壷から骨を出してサラシに巻いて納骨している場合や遺骨をそのまま土に還している場合もあります。
遺骨をそのまま土に還している場合などは、慣れていないと回収が困難なので専門の石材店などに依頼すると安心でしょう。
地域によって骨壷に入れる遺骨の考え方やカロートに安置する方法の考え方や風習が異なるので、それぞれの地域の方法により取り出す必要があります。
遺骨をお墓から取り出す際の注意点

遺骨をお墓から取り出す際には、次のような点に注意する必要があります。
事前に家族や親族、墓地の管理者に相談する
墓じまいはご自身だけの問題ではないので、家族や親族含めた関係者の了承を必ず得る必要があります。
勝手に墓じまいをすることで、親族間のトラブルになる恐れがあります。
また、墓地やお寺の住職、お墓の管理者などに事前に墓じまいの意思があることを相談しておくと良いでしょう。
勝手に墓じまいをすることで、離壇に関するトラブルが発生することもあるので、手続きがスムーズに進行できるように事前に相談を忘れないようにしましょう。
閉眼供養をする
お墓に遺骨を入れる際には、墓石に魂を込める法要である開眼供養を行いますが、墓じまいの際には逆に墓石から魂を抜く閉眼供養を行う必要があります。
閉眼供養の法要は、現在では省略する場合もありますが、石材店の中には閉眼供養をおこなわないと遺骨を取り出してくれない場合もあります。
閉眼供養は必ず行わなくてはならないことではないので、必要の有無は事前に確認しておきましょう。
石材店では遺骨の預かりをしない
墓じまいの際に遺骨を処分する場合や、遺骨を他の場所に移動させるために、一時的に石材店に遺骨を預かってもらおうと考える方もいらっしゃいますが、石材店で遺骨は預かったり引き取りなどは行いません。
遺骨の処分などの移動にはそれぞれ規則があるので、ルールに沿って管理する必要があります。
遺骨の管理に困ったからといって、自宅敷地内に埋めたり山に勝手に埋めたりすると 「墓地、埋葬等に関する法律」に対する違反事項となり、懲役を6箇月以下の懲役または5千円以下の罰金になるので取り扱いには注意しましょう。
遺骨の汚れを綺麗にする
骨壷を取り出す際や、地面に埋まった遺骨を取り出す際には、汚れが付着していないか十分に確認して取り出す必要があります。
遺骨が汚れている際には、綺麗にしておきましょう。
頻繁に手にするものではないので、蓄積された汚れが付着している場合もあります。
梱包など行い、輸送をする際に、汚れが悪臭の原因となるので必ず拭き取り掃除をしましょう。
身元が分からない遺骨が安置されている場合もある
墓じまいの際には、お墓の中に安置されている全ての遺骨を取り出します。
改葬許可申請書に管理していた全ての先祖の名前を記載する必要がありますが、名前のない骨壷などがでてくることもあり申請に困ってしまうこともあります。
このような場合には、氏名欄に「不詳」と記載すれば良いので、分からないからといって勝手に山などに埋めたり処分を行わないようにしましょう。
まとめ
墓じまい後の遺骨の供養方法や、遺骨の取り出し方、取り出す際の注意点について解説しました。
墓じまいの後は、遺骨をカロートから取り出してそれぞれ事前に決めた供養方法を行います。
お墓の中には、今までお世話になった家族やこれまで関係性がなかった先祖の遺骨など様々な遺骨が安置されているので、敬う気持ちを忘れず納得のいく供養方法を行うことが必要です。
墓じまいを実施した後には、遺骨を手元に安置する方法と手元には置かずに永代供養や散骨などの方法で遺骨を処分する供養があります。
どのような方法で供養を行うのかは、生前の故人の意向や生き方などで決めたり、残された遺族やその親族などでよく話し合いをして決めると良いでしょう。
散骨を選択された場合には、ご自身で散骨作業を行うと自治体などでは禁止されている地域の確認が難しいので、専門の業者に相談すると安心です。