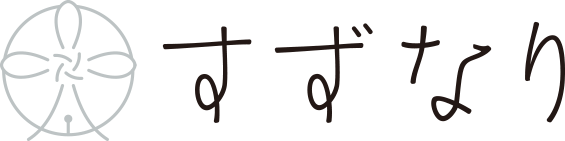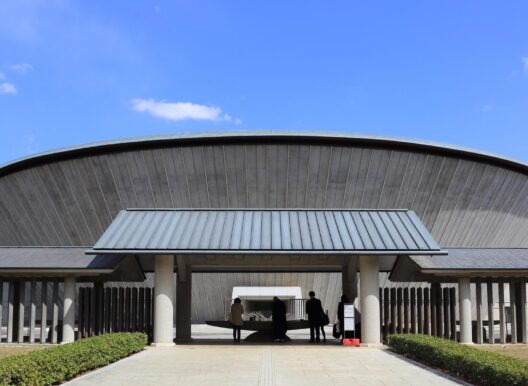火葬の後・葬儀の後など、遺骨を持ち歩かなければいけない時に、遺骨をどのように持ち歩く・扱うべきか分からないと感じる方もいるでしょう。
遺骨の持ち運びには、何らかのルールがあるのでしょうか?
今回の記事では、遺骨を持ち歩く方法と、持ち運びに使えるアイテムや注意点について詳しくまとめました。
これから遺骨を持ち運ぶ機会がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
遺骨を持ち歩くタイミングの具体例
遺骨をお墓に納めてから取り出し、持ち歩く機会はそう多くはないです。
しかし、以下のようなタイミングで遺骨を持ち歩かなければいけないことがあるでしょう。
- お墓の引越しをするとき
- 火葬後の遺骨を自宅に持ち帰るとき
- 墓じまい後に永代供養や粉骨をするとき
お墓の引越しをするとき
核家族化が進んだ今では、現在のお墓が遠方にあり、住まいの近くにお墓を移動することでお墓を管理する手間を減らしたいと考える方が増えています。
お墓のお引越しでは、既存のお墓がある場所から新しいお墓を建墓する場所まで、自分で遺骨を持ち運ぶことになるでしょう。
移動距離によっては、遺骨を持ったまま飛行機で移動しなければいけません。
火葬後の遺骨を自宅に持ち帰るとき
火葬場で火葬した遺骨は、原則として遺族が自宅に持ち帰り納骨まで保管します。
一般的には、持ち帰った遺骨は祭壇に安置し、四十九日の法要後にお墓などに納骨します。
墓じまい後に永代供養や粉骨をするとき
お墓の管理や継承が難しいという理由で、墓じまいを決めるご家庭も増えています。
墓じまいをした後には、永代供養をお寺に依頼する・粉骨業者や散骨業者に依頼して遺骨を供養するときなど必要となるでしょう。
墓じまい後にお墓から取り出した遺骨は、自分で自宅または次の納骨先まで持ち運ばなければいけません。
遺骨を持ち歩いて良いのか?

そもそも、遺骨は持ち歩いて良いものなのでしょうか?まずは遺骨の持ち歩きの可否について説明します。
遺骨を持ち歩く行為自体に問題はない
遺骨を持ち歩くことは、法律上のみでなく宗教上も問題がない行為です。
「遺骨を持ち歩くことは罰当たりなのでは?」
「遺骨を持ち歩くと故人が成仏できなくなってしまうのではないか?」
など不安になる方もいるようですが、そのような心配は不要です。
遺骨を捨てる・自由に埋葬することは法律違反
遺骨の持ち歩きを罰する法律は存在しませんが、自分で遺骨を捨てたり許可を得ていない場所に埋葬したりする行為は、「墓地、埋葬に関する法律」・「刑法」違反になります。
遺骨の埋葬は、自分の庭や畑など所有地であっても認められないことを知っておいてください。
遺骨を持ち歩く時の使いやすいアイテム

遺骨は火葬後に骨壷と骨箱に入れられます。
遺骨を持ち運ぶ際には、骨箱のままではなく、次のようなアイテムを活用すると良いでしょう。
風呂敷
骨箱を持ち運ぶ際に使う代表的なアイテムが風呂敷です。
風呂敷で骨箱を持ち運ぶことは一般的であり、使用後の風呂敷は小さく折り畳めるというメリットがあります。
ただし、風呂敷に包まれた骨箱は形状が分かりやすく、「遺骨を運んでいること」を隠したい方には向いていません。
遺骨専用バッグ
骨箱用の専用バックは骨箱がピッタリフィットする形状で作られています。
バッグはインターネットまたは葬儀社で購入可能です。
遺骨の専用バッグの中には、小さく折り畳みできるもの・撥水加工が施されているものなどさまざまな種類があります。
保冷バッグ
大きめの保冷バッグを、骨箱を入れる袋に使うこともできます。
遺骨を持ち運んでいる事実を周囲に知られたくない方におすすめの方法です。
ただし、専用ではない袋に遺骨を入れる行為に、抵抗を感じる方もいるようです。
車・電車・バスなどシーン別の遺骨を持ち運ぶ方法

遺骨を持ち運ぶ時には、以下の注意点を把握しておきましょう。
ここでは、遺骨を持ち運ぶシーン別に紹介します。
遺骨を車で持ち運ぶ場合
遺骨を車で持ち運ぶ場合には、遺骨を座席に置いたりトランクに入れたりせずに、喪主または親族が抱きかかえてください。
自分が運転手であり、同乗者がいない状態で遺骨を運ぶ時には、遺骨が倒れないようにシートベルトでしっかり固定して座席に置きます。
運転中に遺骨が席から落ちたり倒れたりすることを防ぐために、細心の注意を払いながら運転しましょう。
遺骨を電車やバスなどの公共交通機関で持ち歩く場合
電車・新幹線・バスなどの公共交通機関で遺骨を持ち歩く場合には、他の乗客に配慮をすることが大切です。
骨箱のまま持ち歩くのではなく、専用の袋や風呂敷に入れて丁寧に扱い、他の乗客にぶつからないように注意しましょう。
落下の恐れがあることから、電車内の網棚には置かないようにしましょう。
座席に座る時には、遺骨を自分の膝の上において抱きかかえます。
遺骨を飛行機で持ち運ぶ場合
遺骨に関する扱いは、航空会社によって異なります。
事前に問い合わせをして、火葬許可証など提出が必要な書類を準備しておきましょう。
機内に持ち込んだ遺骨は、骨箱のサイズによって座席上の共用収納棚に入れなければいけません。
また、遺骨を海外に持ち込む・海外から持ち込む場合には、各国のルールに従って必要な書類を集めてください。
遺骨を持ち運ぶ時の注意点

遺骨を持ち運ぶ際には、以下の点を意識しましょう。
骨壷が壊れないように慎重に運ぶ
遺骨を入れる骨壷には、衝撃のせいで割れ・ひびが入る可能性があります。
遺骨は慎重に持ち歩き、落としたりぶつけたりしないようにしましょう。
大人の遺骨は骨壷などを入れて3kg以上の重さになることから、遺骨を持つまたは抱えた状態で長時間過ごすことは避けた方が無難です。
人が多い場所では配慮が必要
遺骨に関する考え方は、人によって変わります。
そのため、遺骨を見て気分を害する方もいるでしょう。
そのため公共交通機関や公共の場に遺骨を持ち込む時には、周囲の方への配慮が欠かせません。
遺骨を持っていることが分かりにくい袋に入れておけば、遺骨を持ち運んでいる事実を周囲の人に知られずに済みます。
遺骨を宅配便で送る方法と注意点

遺骨を自分で持ち運ぶことが難しい場合には、宅配便で遺骨を送るという手段を選びます。
遺骨の宅配を扱わない業者もあるため、国内の場合は「ゆうパック」を使うと良いでしょう。
ここでは、ゆうパックで遺骨を宅配する時の手順や注意点をまとめました。
ゆうパックで遺骨を送る方法
ゆうパックで遺骨を送る場合には、通常の荷物の料金が適用になります。
発送前に遺骨が溢れない・割れないようにしっかり梱包してください。
荷物の品名には「遺骨」と明記し、贈り伝票の「われもの」「逆さま厳禁」「下積み厳禁」に丸をつけることも忘れないようにしましょう。
遺骨をゆうパックで送る時の送料目安
ゆうパックで遺骨を送る時には、大きさ・重さ・送り先までの距離で送料が変わります。
ゆうパックの荷物は、縦・横・高さの長さを合計して、60cm以下なら60サイズ・80cm以下なら80サイズのようにサイズが決定します。
それより大きいサイズには、100、120、140、160サイズが小刻みに用意されています。
ゆうパックの荷物の重さは、25kgまでは通常料金であり、25kg〜30kgのものは「重量ゆうパック」としての加算料金を払わなければいけません。
上記のサイズ・重さの要素に加えて都道府県別の基本運賃表に準じた料金が設定されており、送り先が遠方になるほど料金が上がります。
例えば、25kg未満・サイズ80の場合は約1,000円〜1,700円の配送料です。
正確な送料を知りたい方は、サイズ・重さ・送り先をもとに日本郵政の公式サイトで確認してみてください。
遺骨をゆうパックで送る時の注意点
遺骨をゆうパックで送った時に何らかのトラブルが発生し、損害を受けた場合には遺骨の補償を受けられません。
なぜなら、遺骨には値段がつけられないためです。
骨壷や骨箱のみの補償は受けられる可能性はありますが、トラブル発生時の補償が気になる方は、配送ではなく持ち込みを選ぶべきです。
遺骨を自宅に持ち帰ってから実施するべきこと

自宅に持ち帰った遺骨は、四十九日まで自宅で保管するケースが多いです。
ここでは、四十九日までの遺骨の扱い方について説明します。
仏間に後飾り祭壇を作って安置する
仏間がある場合には仏間、仏間がないご家庭ではリビングや寝室の一角に遺骨を安置するスペースを作ります。
この際、可能であれば「後飾り祭壇」という遺骨を置いておく台を用意しましょう。
後飾り祭壇の飾り方は家庭や地域によって異なりますが、以下のような飾り方が一般的です。
- ご遺骨:上段
- 白木位牌・遺影:上段または中段
- 仏具・お供え:中段または下段
遺骨は仏壇の中に飾るべきではない
仏壇があるお宅では、遺骨を仏壇の中に飾ろうと考える方もいます。
しかし、仏壇は信仰の中心である本尊を祀るために存在することから、故人の遺骨を飾る場所として適しません。
遺骨を仏壇の近くに置く場合には、仏壇の中ではなく仏壇の隣に後飾り祭壇を作りましょう。
カビや直射日光に注意する
遺骨は湿気や寒暖差に弱く、管理方法を間違えるとカビが生えてしまう恐れがあります。
湿気が多い場所や直射日光が当たる場所には、遺骨を安置しないようにしてください。
また、火葬後の遺骨は無菌状態ですが、遺骨に素手で触れる・骨壷に結露が起こることでカビが生える可能性が考えられます。
カビが心配な方は、遺骨を粉状に砕いた上で真空パックにする処置を検討しましょう。
遺骨を常に持ち歩きたい時にはどうすれば良いのか

遺骨を常に持ち歩く供養の方法を「手元供養」と呼びます。
手元供養では、自宅に遺骨を置いたり身につけたりして故人を偲びます。
ここでは、代表的な手元供養の方法を説明しましょう。
遺骨でペンダントを作る
遺骨ペンダントには、遺骨を加工して人工のダイヤモンドをアクセントにしたタイプと、小さなカプセルの中に少量の遺骨を入れるタイプがあります。
どちらも一見して「遺骨ペンダント」とは気づかれないため、安心して普段使いできるでしょう。
ミニ骨壷に入れて持ち歩く・オブジェにする
持ち運び用またはオブジェとして使えるミニ骨壷に遺骨を入れて、手元供養をするという手もあります。
手元供養用のミニ骨壷は、デザイン・サイズが豊富であり、中にはゴルフボール程度の持ち歩きやすいものも存在します。
多くのミニ骨壷は、骨壷に見えないようなデザインなので、人目についても問題ないでしょう。
すずなりのミニ骨壷
手元供養の注意点
手元供養は故人の遺骨全てではなく、遺骨の一部に限られるケースが多いです。
なぜなら、遺骨全てを手元に置いておく・持ち歩くことは現実的でないためです。
遺骨を分ける行為を「分骨」と呼び、手元供養をする遺骨以外は墓地や納骨堂、散骨などの供養方法が選択されます。
また、手元供養の遺骨を肌身離さず持ち歩く時には、紛失に注意してください。
特に遺骨アクセサリーは非常に小さいことから、無くしてしまった遺骨は2度と取り戻せない可能性が高いです。
手元供養であれば、常に故人の存在を感じながら生活を送れるでしょう。
まとめ
遺骨の持ち運びに、法律や宗教上の問題はありません。
火葬後・葬儀後・散骨時など遺骨の移動が必要な際には、この記事を参考にして正しく遺骨を持ち運びましょう。
また、遺骨を持ち運ぶ際の注意点を意識し、遺骨や骨壷を損傷しないように注意を払うだけでなく、周囲の人に不快な感情を与えない配慮をしてください。