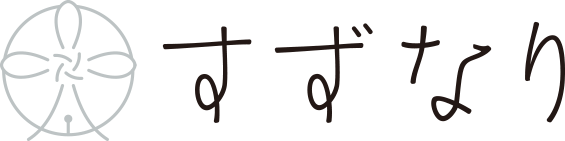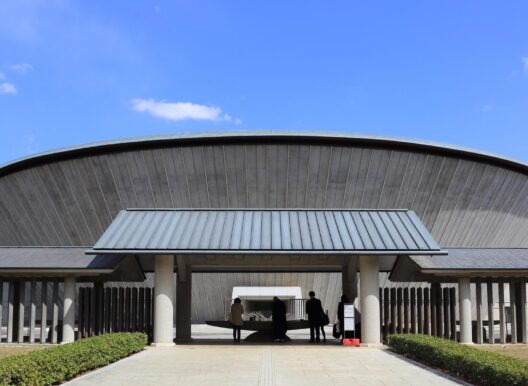先祖から受け継いだお墓に後継者がいないため墓じまいを選択した際に、お寺からの離檀が必要なことを知らずにトラブルになったなどのようなことをよく聞きます。
故人を供養する方法を真剣に考えている際に、余計なトラブルになることは避けておきたいものです。
ここでは墓じまいの時にお寺に離檀を伝える方法や、離檀で揉めた場合の対処方法、離檀トラブルを避けるポイントなどを解説します。
墓じまいにおける離檀とは?
お墓がお寺にある場合には、一般的にその寺院の使徒になりお布施や会費などを支払って、経済的に寺院を支える檀家に入る必要があります。
檀家に入ることで、お葬式や法事などの供養をしてもらうことができます。
一方で、墓じまいやお墓の移転などで檀家を離れることを離檀と言います。
お墓は先祖代々受け継がれてきたものが多いので、昔から特定の寺院の檀家であることが多くあります。
しかし、近年では故郷から離れて暮らす方の増加や宗教を問わない民間の墓地なども増えたことにより離檀を選択する方も多くなっているようです。
お寺に離檀の意思を伝える際の交渉方法

従来までは、今まで先祖を供養する際にお世話になったお寺に対して離檀を行うことは縁起が悪いようなイメージを持たれていましたが、近年では生活環境や供養方法の多様化に伴い離檀は珍しいものではなくなってきました。
しかしながら、お寺からするとサポートしてくれる檀家が減ることになるのであまり良く思われない事もあります。
そのために、お寺に離檀の意思を伝えるためには以下のような方法で交渉すると良いでしょう。
「離檀したい」ではなく相談したいという姿勢で連絡をする
お寺にとっても、檀家は過去より先祖の供養を行い、遺骨を守ってきたとても大切な存在です。
そのために、一方的に「離檀します」などと決定事項を報告されるとあまりよい気持ちにはなりません。
離檀の意思を伝える際には、お墓参りできていない現状や、お布施などが納められなく経済的に苦しい状況などを説明し、離檀を選択せざる得ない状況を打ち明ける相談から始めると良いでしょう。
無縁仏になる可能性がある状況を伝える
近年問題視されているのは、核家族化や少子化により将来的にお墓を承継する人がいなくなり無縁仏になる可能性が増加していることです。
無縁仏になることで、お墓がメンテナンスされないばかりか管理費等もお寺に支払えなくなる恐れがあります。
適切な時期に離檀をおこなわないと、将来的にお寺に迷惑をかけることに繋がるのでその旨を丁寧に訴えましょう。
お寺にとっても無縁仏を増やすと、その土地を更地に戻すなどの費用を代わりに負担することになるので事前に相談し説明することで理解を得られるでしょう。
今までお墓を守ってくれた感謝を伝える
お寺は先祖代々お墓を守ってきてくれた大切な存在です。
葬儀の際には、どのような時にもすぐに駆けつけてきてくれ読経や法話などで遺族の気持ちを慰めてきてくれました。
そのことに対して、誠心誠意感謝の気持ちを伝えることが大切です。
ご自身がお寺と深い関係になくても、先祖代々繋がってきた気持ちを大切にしましょう。
感謝の気持ちは直接伝えることが望まれますが、遠方に住んでいる場合などは電話でお礼を述べた後に感謝の手紙を送付するとより丁寧になるので誠意を示すことができます。
離檀でよくあるトラブルと揉めてしまった時の対処法

お寺は故人の遺族と共にお墓を守り続けてきた存在なので、お墓の管理人のような扱いをしてしまうとトラブルになることもあります。
離檀でよくあるトラブル
離檀の際によくあるトラブルは、次のようなものがあります。
法外な離檀料金を請求される
離檀によるトラブルで最も多いのが、離檀することによる離檀料が200万円〜400万円など高額な金額を請求されるケースです。
離檀する際に、お寺に対して適切な相談を行うことが大切ですが、突然墓じまいするので離檀しますなど結果だけ突きつけるなどの対応をするとお寺を怒らせてしまい、結果的に法外な離檀料を請求されることがあります。
【参考】墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意(国民生活センター)
埋葬証明書を発行できない
離檀料はお布施になるので、必ず支払わなくてはならない費用ではありません。
しかし改葬証明書や埋蔵証明書は、墓じまいなど墓地から遺骨を移す際に必ず必要になります。
改葬証明書の発行は各地方自治体の役場で発行しますが、そのための書類には墓地管理者の署名と捺印が必要になります。
また、墓地管理者が発行する埋葬許可証も必要になるので、お寺が離檀を認めない場合には各証明書が発行できないので遺骨を取り出すことができない事態になります。
墓石業者や解体業者が入れない
お墓を残したままで離檀すると、残されたお墓は無縁墓として処理されてしまいます。
そのために必ず墓じまいをする必要がありますが、お寺の中の敷地に入るにはお寺の許可が必要なので、お寺と良好な関係ではない場合には墓石業者や解体業者が入れなく、離檀の進行を進められなくなる問題なども発生します。
離檀を止める権利はお寺にはありませんが、意図的に離檀させない対応をするお寺も中にはあるようです。
また、お寺によっては「指定石材店制度」というものがあり、墓石の購入や建立をあらかじめ決められた石材店でしか行えないという制度があるので、ご自身で選定した業者にお願いすることができない場合もあります。
離断トラブルの対処方法
離断トラブルの対処方法としては、以下のような対処方法があります
法外な離檀料金を請求された場合
離檀料は基本的にお布施になるので、支払いの義務はありません。
高額な費用請求をされたとしても、法的に支払う義務が発生しないので支払う必要はありません。
古くからお墓が寺院にある場合は、契約書などほとんど存在しませんが、新しい寺院などでは契約書などを用意している場合があるのでサインした記憶がある場合には契約書の内容を見返しましょう。
高額な離檀料を請求された場合は、個人で悩まずに消費生活センターや弁護士に相談すると良いでしょう。
離檀させない悪質な対応を受ける
離檀料は前述の通り支払いの義務はありませんが、従来よりお墓を守って頂けたことに対する感謝の気持をお布施として支払うものです。
金額面で折り合いがつかない場合などは、悪質なお寺など埋葬証明書の発行を断る場合もあります。
お寺の対応が悪い場合には、役所の担当者、墓じまい代行、石材店、弁護士などを間に立てて話し合いをすると解決の近道が見えるかもしれません。
寺院が墓じまいの改修工事の許可を出さない
お寺の敷地は、当然のことですが寺院の所有地なので勝手に業者の手配を行ってお墓の改修工事などはできません。
離檀させないために、工事をさせないような行為をするお寺なども中にはあります。
しかし、故人の遺骨の所有権は遺族にあるので、お寺が遺骨を返却できないような態度を続けるようであれば、弁護士を雇い遺骨返還請求訴訟などを行いましょう。
離檀トラブルを避けるポイント

離檀トラブルを避けるには、以下のようなポイントに注目してみましょう。
離檀料の相場や支払い義務について正しい知識を持つ
離檀料は、前述の通り今までお世話になったお寺に対して任意で気持ちをお渡しするお布施になります。
一般的には、他の法要と同じ程度の3万円〜20万円が離檀料の目安とされています。
墓地に関する使用契約や、寺院墓地規則に離檀料の定めが記載されていない限り、離檀料について支払わなくてはならない明確な法的根拠はありません。
そして、離檀料については過去からの慣習となっている場合が多く、特に書面での契約や規則に金額等記載されていることはほとんどありません。
一方で、離檀料を支払う義務はありませんが、先祖代々お墓を守り供養してくれたお寺に対して感謝の気持ちを示すことなく墓じまいをしてしまうのもお寺側としては快くはないでしょう。
ご自身が負担になるほどの高額な金額を支払う必要まではありませんが、お寺側とご自身が納得できる程度の感謝の気持ちを示すと良いでしょう。
お寺に対して丁寧な対応を図る
離檀と決意した時点で早い段階でお寺に相談にいきましょう。
日頃からお世話になっていたことに対する感謝の気持ちと、離檀に至った経緯と理由を順立てて丁寧に説明しましょう。
この際に、離檀料に関する具体的な金額や支払い方法、遺骨の取り扱いや墓じまいを実施するタイミングなどについての詳細も話し合います。
円滑に離檀するために、お寺側と密に連絡をとり双方が納得できる条件で取り進めると良いでしょう。
離檀トラブルになった際の相談先

離檀トラブルになった際の具体的な相談先は、以下のような方になります。
お寺の総本山に相談
お寺には、必ず宗派の元締めとなる総本山があります。
離檀トラブルなどにより法外な離檀料請求や、墓じまいに対する妨害行為などの原因がお寺にある場合には、管轄する総本山に相談する事でサポートが期待できます。
お寺がある地区の役所や国民生活センターに相談
埋葬許可証などの行政手続きが滞る問題が発生している場合での離檀トラブルでは、役所に相談することで対応してもらえることがあります。
自治体により埋葬証明書なしで改葬許可証を発行してくれる場合もあります。
国民生活センターでは、過去に離檀トラブルが発生した事例の紹介や注意喚起情報などもあります。
直接電話で相談したい場合にも、消費者ホットラインなどがあるので利用すると良いでしょう。
墓じまいや供養サポートの専門業者に相談
墓じまいや供養サポートの専門業者では、複数の寺院や墓地をみてきています。
墓じまいや離檀などにも携わる業種になるので、多くのトラブルにも対応しています。
過去に発生した同様のトラブルや、それに伴う解決方法なども熟知している事もあるので適切なアドバイスを受けれる可能性があります。
まとめ
墓じまいの時にお寺に離檀を伝える方法や、離檀でモメた場合の対処方法、離檀トラブルを避けるポイントなどを解説しました。
従来、離檀は縁起が悪いなどという考えがありましたが、故人をきちんとした形で供養したいという考えを優先にしたからこそ離檀という選択に辿り着いています。
その気持ちを丁寧にお寺に説明する事で、トラブルを軽減することができます。
離檀を選択した時には、今まで先祖を供養して頂いた気持ちをお布施で離檀料としてお寺に支払います。
その際に、お寺と良い関係ではない場合には、高額の離檀料を請求される事もあります。
万が一、お寺と離檀料でトラブルになった際には、お寺の総本山や役所の他に、墓じまいや供養サポートの専門業者に相談するようにしましょう。