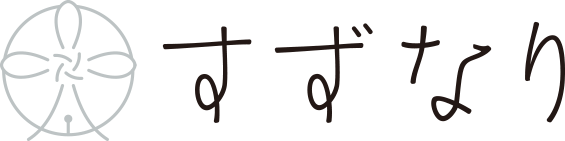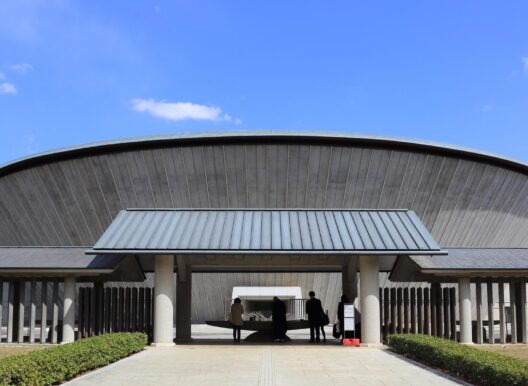お墓には1つのお墓に納骨可能な遺骨の数に対して、法律でルールは設定されていません。
しかし、お墓の納骨室(カロート)に遺骨が物理的に入りきれなくなってしまった時には、そのお墓が「いっぱい」な状態だと言えるでしょう。
カロートはコンクリートや石などで作られており、さまざまなサイズがあります。
この記事では、お墓が遺骨でいっぱいになってしまった時の対処方法についてまとめました。
先祖代々のお墓を受け継いでいる方やこれからお墓を建てようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
お墓のカロートには何人分の遺骨が入るのか
お墓のカロートのサイズは法律で定められていません。
一般的なお墓のカロートには平均して約6〜8人の骨壷を納骨できます。
前後左右のスペースをうまく使えば、約10名の骨壷が納まるケースもあるでしょう。
つまり、建墓した代のご夫婦から3〜4世代が一つのお墓に眠れる計算になります。
ただし、地域の慣習や墓地の規約で納められる遺骨の人数を制限している可能性もあることを知っておいてください。
お墓に入る遺骨の数は法律で定められていない
お墓に入る遺骨の数は、お墓に関する法律である「墓地埋葬法」で定められていません。
そのため、法律上はお墓に定員はないと言って良いでしょう。
しかし、物理的にお墓のカロートに入れられる遺骨の数には限度があります。
先祖代々長く受け継がれているお墓ほど、いっぱいになりやすいと考えてください。
お墓のカロートの拡張は簡単ではない
お墓のカロートを拡張することは不可能ではありません。
しかし、お墓が存在する状態でカロートを工事・拡張はできないため、一度お墓を撤去してからの工事になります。
そのため、新しいお墓を建て直す場合と同程度の費用がかかってしまうでしょう。
お墓に愛着があるなど特殊なケースを除いて、カロートの拡張工事は難しい選択肢であると言えます。
お墓のカロートがいっぱいになってしまった時の対処法

お墓のカロートがいっぱいになってしまった時には、次のような対処法を選択できます。
親族でしっかり話し合い、全員が納得できる方法を探してください。
洗骨・乾燥・粉骨して骨壷を小さくする
粉骨とは、遺骨を細かく砕いてパウダー状にすることを指します。
粉骨した遺骨は元のサイズよりも小さくなるため、骨壷自体をサイズダウンしてカロートにスペースを増やせるのです。
具体的には、直径22cm程度の骨壷に納められていた遺骨は、粉骨後直径15.5cm程度の骨壷に納められます。
現在安置されている骨壷の量が多ければ、その分カロートのスペースも空けられると考えてください。
遺骨の粉骨にかかる費用は元の骨壷のサイズ・粉骨時の立ち合いの有無・乾燥や洗浄の有無によって異なりますが、1万円〜3万円が相場です。
コスト面を見ても、遺骨を別の場所で埋葬したり新しいお墓を建てたりするより、ハードルが低い決断だと言えるでしょう。
お墓を変更せずに「遺骨をお墓に納骨して弔う」ことを継続できます。
納骨堂への引っ越し
遺骨の一部または全てを納骨堂に引っ越しします。
納骨堂とは、建物内に遺骨を安置する設備であり、ロッカー型・仏壇型などさまざまな形式のものが用意されています。
永代供養も依頼できるプランも選択可能で、お墓の後継者がいなくなっても施設に供養を続けてもらえます。
遺骨を全て納骨堂に引っ越せば、今後のお墓のお手入れからの負担がなくなるでしょう。
駅前など利便性が高い納骨堂を探すことで、お墓参りのハードルも下げられます。
散骨
散骨は粉骨後の遺骨をお墓に戻さず、海や山などに撒いて供養することを指します。
散骨専用業者に依頼すれば、散骨時のルールを守り近隣住民に対して適切な配慮をした散骨ができるでしょう。
ただし、散骨後の遺骨は取り戻せない・手を合わせる対象がなくなってしまうなどのデメリットもあるため、十分な検討が必要です。
散骨は親族から理解が得られないケースが多く、トラブルにつながる恐れがあることを知っておかなければいけません。
樹木葬(永代供養)
墓石の代わりに、樹木や草花を墓標としたお墓に遺骨を埋葬することを樹木葬と呼びます。
樹木葬は永代供養付きのプランが多く、お墓の管理が難しくなったご家族におすすめの選択肢の一つです。
他の方の遺骨も一緒に供養される集合型であれば、より手頃な価格で供養を続けられるでしょう。
古い遺骨を一つにまとめる
古い遺骨を一つにまとめて、新しい骨壷を納めるスペースを増やすことも可能です。
一般的には50回忌を経過した遺骨は「弔いあげ」と呼ばれる法要を済ませた後、仏事を行う必要がなくなります。
弔いあげ後の遺骨は、永代供養に移行するケースが多いです。
お墓の中で50回忌を終えた遺骨を一つにまとめれば、新しい遺骨を安置できるようになるでしょう。
ただし、一度まとめてしまった遺骨を再度分別することはできません。
新しいお墓を建てる
より大きなカロートを持つ新しいお墓に遺骨を全て移動させる「改葬」をすれば、新しいお墓でより多くの遺骨を安置できるようになります。
ただし、建墓費用の目安は200万円、さらに古いお墓の撤去費用や閉眼供養・開眼供養のお布施も用意しなければいけません。
お墓の建て直しには、多くの費用がかかると言って良いでしょう。
お墓が遺骨でいっぱいになった時におすすめできない対処法

お墓が遺骨でいっぱいになった時に、おすすめできない対処法には次のようなものがあります。
もちろん選択可能ではあるものの、十分な検討とデメリットの理解が必要です。
遺骨を粉骨してカロート内に撒く
カロートが全面コンクリートではなく一部が土になっている場合には、遺骨を粉骨してカロート内に撒いて土に還すという手段があります。
結果的にカロートのスペースが確保でき、遺骨を同じ場所に置いておける方法ですが、「遺骨を撒く」行為に対して心理的に抵抗を感じる方もいるでしょう。
さらに、撒いてしまった遺骨を再度集めることはできません。
今後墓じまいをして永代供養や改葬をしようと決めた時に、撒いた遺骨は持ち出せないのです。
また、粉骨をせずにカロート内に撒かれた遺骨は、土に還るまでに何百年もの年月が必要です。
安易に手元供養をする
遺骨を自宅などで供養する手元供養には、特別な費用がかかりません。
手元費用に適したおしゃれな骨壷を用意したり、遺骨を加工してペンダントにしたりしても、費用は10万円以内で抑えられるでしょう。
しかし、手元供養を「安く遺骨を管理できる方法」だと考えるのは危険です。
遺骨を自宅保管していると、カビが生えてしまう・災害発生時に遺骨を紛失してしまう恐れがあるのです。
さらに、手元供養をしていた本人が亡くなった場合には、残された遺族はその遺骨の管理に戸惑ってしまいます。
手元供養は、自己管理の方法・自分が亡くなった後の管理についてもよく考えた上で決定するべきです。
粉骨について

この章では、遺骨を砕きパウダー状にする粉骨について詳しく説明します。
遺骨の粉骨を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
粉骨の方法と流れ
粉骨業者の中には、手作業粉骨・一般粉骨の2つのプランが用意されているケースが多く、手作業粉骨プランでは金属刃などを使用せずに乳鉢と乳棒を使って丁寧に遺骨を細かくしていきます。
また、一般粉骨の場合は機械を用いて遺骨をパウダー状にします。
多くの業者では、手作業粉骨時のみ遺族の立ち合いを希望可能です。
粉骨は自分で行うことも可能ですが、精神的な負担が大きい・適切な処理が必要なことから、専門業者に依頼するべきです。
粉骨後に不要になった骨壷の処分方法
粉骨後には骨壷のサイズが小さくなるため、これまで使用していた骨壷が不要になります。
骨壷はあくまで遺骨の入れ物であり、不燃物として処分して構いません。
しかし、骨壷の処分に抵抗を感じる方もいるでしょう。
骨壷の処分に抵抗を感じる方は、葬儀社や石材店に骨壷の処分を依頼すると良いです。
まとめ
お墓のカロートのサイズはお墓によって異なりますが、遺骨を安置できる人数に物理的な限界があります。
お墓のカロートが遺骨でいっぱいになってしまった時には、遺骨を粉骨して骨壷のサイズを小さくする・一部または全ての遺骨を納骨堂など別の場所で供養する・粉骨済みの遺骨を散骨するなどの手段があるでしょう。
遺骨の扱いについては自分のみでなく家族・親族と十分話し合いをして、全員が納得できる決断をしてください。
自分だけで遺骨の扱いを決めてしまうと、将来的に親族間のトラブルにつながる可能性が考えられます。
お墓は一族全員が手を合わせる対象である事実を理解し、慎重に今後の対応を決めましょう。